30.Apr.2025
[PR]
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
28.Dec.2006
クリスマスのケーキ。
クリスマスのケーキ。
23.Dec.2006
Beatlesが教えてくれた
Beatlesが教えてくれた
1969年、ビートルズとして最後のライブ演奏となったrooftop concert(彼らのレーベル「アップル」のビル屋上でのゲリラライブ)の模様をYOUTUBEでどうぞ。
その1
その2
その3
このビルの所在地は、ロンドンの中心Savile Row (背広でおなじみ)。昼間のビジネス街に、突如爆音をかき鳴らし登場するビートルズ。
人々の反応が、この国を物語っていますね。
というより、ビートルズの国民的スター性を物語っているのでしょうか。
「art」に寛容なお国柄は、今年5月にロンドンを舞台に繰り広げられた巨大人形劇「サルタンの象」でも実証済みです。
ロンドンの町を練り歩く巨大像(高さ12m)はもとより、ダブルデッカー(赤い2階建てバス)に乗ってロンドン観光する巨大少女(5m)がおもしろくてしょうがないのですが、そのために町中の交通を規制してしまうロンドンがまたおもしろい。
主催劇団が説得に2年を費やしたそうですが、それにしたって万事完璧な規則のもとに成り立っているニッポンだったら、モロモロの事情により結局許可が下りなかった・・・ということで落ち着きそうですが、どうでしょう。
こういうところが何事にもいい加減なイギリスならではの長所ですね。
これがあるから、まともに運転されたためしのないハチャメチャな地下鉄事情に毎度憤りつつも、何だか憎めないでいるのです。
罪な街です。
この人形劇の詳細はこちらのブログさんでご覧になれます。
05.Dec.2006
物申す音楽。
物申す音楽。
3年前に亡くなった往年の大女優、キャサリン・ヘップバーンがクララ・シューマンを見事に演じた映画「愛の調べ(Song of Love)」(1947)は、史実に基づいたあくまでフィクションです。
つまり、あの中のシューマン、クララ、ブラームスのイメージを鵜呑みにしてはいけないのですが、とにかく映画として非常によかったので、個人的にシューマンとクララの愛をどこかロマンチックで神聖なままにとどめたい想いがどうしても強い私。
映画でテーマソングとなっていたこの「献呈」にも思い入れが深いのです。
フランツ・リストといい、この映画は我々クラシック音楽を愛する者の理想とロマンをカタチにしてくれたような映画です。
映画では、シューマン亡き後、とうとう思い切ってクララに求婚するブラームス。
場所はレストラン。
戸惑うクララのテーブルへヴァイオリン弾きが「一曲いかが」とまわってきます。
偶然にもそのヴァイオリン弾きが奏で出したのは、亡き夫の残した「献呈」。
その音色を聴いて自らの愛と使命を再確認するクララ・・・
自分は、音楽家ロバート・シューマンの妻であるということ。
夫の遺産であるこの素晴らしい音楽を後世に残すこと。
いい音楽は本当にいろんなことを伝えてくれますね。
この映画を共に見た親友フルーティストの川瀬礼実子の父娘デュオが左のオススメCDです。
ようやくイギリスに届いて昨日聴きました。
素晴らしい。
これは誰のモノでもなく、まさに川瀬親子の音楽。
紛れもない彼らの音楽だという実感が、一音一音から伝わってきました。
ボサノバが入っているのが象徴的だと思います。一種抑制の利いた押し付けのない音楽。ゆっくりじんわりあったかく横で笑ってくれているような、そういう音楽なのです。
そしてこれぞ、川瀬親子の生き様なのです。
心がさみし~い問題が多発中の現代社会に、救世主的存在となりますね、このCDは。
人間の心は、こういう音楽によってあたためられるべきなんですよね。
私もこういう音楽を目指す者として、このCDに勇気をもらいました!
我が家のヘビーローテーションです。
27.Nov.2006
チェロと品格。
チェロと品格。
ちょうど今から20年前に亡くなりましたが、
ピエール・フルニエというフランスのチェロ奏者がいました。
昔TVでこの人の壮年期くらいの白黒の演奏映像を見た時、
舞台そでからゆっくり登場するその様を目にしただけでぐっとしびれた記憶があります。
ピアノからチェロに変更するきっかけとなった不自由な足をゆっくり運ばせながら舞台中央に移動するお姿・・・
・・・それは、きちっと結んだお上品なお口を節目がちに上等のナプキンで優雅に拭うような"身に付いた品格"でした。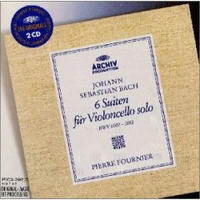
ああいう雰囲気は時代の生んだ芸術なので、もう今の世にはないものなんでしょうね。
ところで、今週の週刊classic vol.21では、チェロ曲の代名詞たるバッハの無伴奏チェロ組曲を紹介しました。言わずと知れた名曲ですね。
フルニエのを一度聴いてみて下さい。
老教師に優しく諭されるような気持ちになります。
チェロといえば、真っ先に頭に浮かんでくる大大大好きな曲があります。
ブラームスのピアノコンチェルト2番の3楽章です。
ピアノコンチェルトなのにチェロが主役になる曲の冒頭、ゆっくりといいソファに深く沈み込みたい気持ちになります。
あのメロディーは絶品です。
ピンとこない方は是非以下をクリックして聴いていただきとう存じます。
チェリビダッケ指揮、ピアノ:バレンボイムです。
ピエール・フルニエというフランスのチェロ奏者がいました。
昔TVでこの人の壮年期くらいの白黒の演奏映像を見た時、
舞台そでからゆっくり登場するその様を目にしただけでぐっとしびれた記憶があります。
ピアノからチェロに変更するきっかけとなった不自由な足をゆっくり運ばせながら舞台中央に移動するお姿・・・
・・・それは、きちっと結んだお上品なお口を節目がちに上等のナプキンで優雅に拭うような"身に付いた品格"でした。
ああいう雰囲気は時代の生んだ芸術なので、もう今の世にはないものなんでしょうね。
ところで、今週の週刊classic vol.21では、チェロ曲の代名詞たるバッハの無伴奏チェロ組曲を紹介しました。言わずと知れた名曲ですね。
フルニエのを一度聴いてみて下さい。
老教師に優しく諭されるような気持ちになります。
チェロといえば、真っ先に頭に浮かんでくる大大大好きな曲があります。
ブラームスのピアノコンチェルト2番の3楽章です。
ピアノコンチェルトなのにチェロが主役になる曲の冒頭、ゆっくりといいソファに深く沈み込みたい気持ちになります。
あのメロディーは絶品です。
ピンとこない方は是非以下をクリックして聴いていただきとう存じます。
チェリビダッケ指揮、ピアノ:バレンボイムです。
26.Nov.2006
頑固なこりに!タイガーバーム。
頑固なこりに!タイガーバーム。
まだ20代前半だというのに、首から背中にかけてのコリがひどい夫。
姿勢のせいもあり、2年以上前の事故の後遺症でもあり。
筋肉痛を癒す入浴剤なども効果なく、ストレッチもいまいち有効でない様子・・・
そんな夫が今さらはまっているのがタイガーバーム。
たまたま妻がBootsで見つけて、懐かしさのあまり購入したところ、このいわゆる万能膏薬の存在さえ知らなかった夫の体質に、湯上りすりこみマッサージがどうやらマッチしたようです。
幼少期に香港のタイガーバームガーデン訪問以来愛用している妻ですが、すりこみは皮膚がひりひりして使えない。
ウソかホントか万病をたちどころに治すというふれこみのタイガーバーム。
奇薬です。
注:"一時的な筋肉痛の軽減に"と書かれてあるところからして堂々と気休めの薬ですけどね。
19.Nov.2006
アルゲリッチ&デュトワ そして古き良き英国紳士たち。
アルゲリッチ&デュトワ そして古き良き英国紳士たち。
昨晩11月17日は、二人でロイヤルアルバートホールにアルゲリッチ&シャルル・デュトワを聴きに行きました。
オケはロイヤルフィルハーモニックオーケストラ。
曲目は、
シベリウス:カレリア組曲
ラヴェル:ピアノコンチェルト
リムスキー・コルサコフ:シェーラザード
運悪く大雨。
学校帰りの夫と、仕事後の妻がTottenham Court Roadの韓国レストランで落ち合ったのは開演40分前!
美味しい激辛メニューを瞬時にたいらげ、口中燃える濡れ鼠となりながらRoyal Albert Hallまで地下鉄とバスを乗り継いで駆けつけました。
こういう時に限って開演時間きっちりにはじまっているもの。
シベリウスのカレリア組曲を惜しくも廊下で聴く羽目になりました。
昨日の目玉はやはりアルゲリッチ。
元夫デュトワのタクトの元で、真っ白になったトレードマークのロングヘアをバサバサかきあげながら、堂々たる落ち着きの演奏でした。
感動が押し寄せるような情熱的な演奏ではなかったし、彼女の無数の名演の中では特筆すべくもない舞台でしたが、そこはやはり世界一級品のアルゲリッチのピアノ、いろんな箇所で唸らされました。
シェーラザードは第一バイオリンが弾くシェーラザードのテーマがどうも乗り切らず、心細い感が残りましたが、とにかく好きな曲なのであれこれ批評せずに楽しく聴きました。
ちなみに聴衆は執念の拍手5回目くらいでアルゲリッチのアンコールを勝ち取りました。
バッハ:イギリス組曲第2番BWV807よりブーレ。超高速でした。
これだけの売れっ子大物の舞台に感動を求めるのは正直難しいところ。しかしながらやはり彼らの舞台からは無数に得るものがあります。
チケット£5~40は安いですね。
イギリスでは幕間に飲食する割合が高い(ほぼ全員?)ので、我々にもすっかりその習慣がついてしまいました。
バーで隣に居合わせたイギリス人老カップル。
紳士の方はスニーカーにフリースのジャケットという軽装ながら、しっかり首には蝶ネクタイ。
イギリスにはやはり腐ってもなんとやらで、こういう伝統を守る人々が多いのは確かです。
老人に古き良きイギリスを見るおもしろい例として。
以前妻がカフェNeroのソファでコーヒーを飲みながら一人読書をしていると、向かいのソファにやって来たのは老紳士。
小汚いカフェの地下で、ティーバッグの紅茶を場違いなほどお上品にお飲みになり、飲み終えるときちんと服を整えステッキを持ち、帽子を片手に、
「Young lady, good day」
本から目だけを上げた無作法な妻に、ていねいにお辞儀をして帰って行かれました。
そんなイギリスの伝統とチャーミングな継承者たちに敬意を表して、我々もコンサートにはほんの少し小奇麗ないでたちで行くのでした。
オケはロイヤルフィルハーモニックオーケストラ。
曲目は、
シベリウス:カレリア組曲
ラヴェル:ピアノコンチェルト
リムスキー・コルサコフ:シェーラザード
運悪く大雨。
学校帰りの夫と、仕事後の妻がTottenham Court Roadの韓国レストランで落ち合ったのは開演40分前!
美味しい激辛メニューを瞬時にたいらげ、口中燃える濡れ鼠となりながらRoyal Albert Hallまで地下鉄とバスを乗り継いで駆けつけました。
こういう時に限って開演時間きっちりにはじまっているもの。
シベリウスのカレリア組曲を惜しくも廊下で聴く羽目になりました。
昨日の目玉はやはりアルゲリッチ。
元夫デュトワのタクトの元で、真っ白になったトレードマークのロングヘアをバサバサかきあげながら、堂々たる落ち着きの演奏でした。
感動が押し寄せるような情熱的な演奏ではなかったし、彼女の無数の名演の中では特筆すべくもない舞台でしたが、そこはやはり世界一級品のアルゲリッチのピアノ、いろんな箇所で唸らされました。
シェーラザードは第一バイオリンが弾くシェーラザードのテーマがどうも乗り切らず、心細い感が残りましたが、とにかく好きな曲なのであれこれ批評せずに楽しく聴きました。
ちなみに聴衆は執念の拍手5回目くらいでアルゲリッチのアンコールを勝ち取りました。
バッハ:イギリス組曲第2番BWV807よりブーレ。超高速でした。
これだけの売れっ子大物の舞台に感動を求めるのは正直難しいところ。しかしながらやはり彼らの舞台からは無数に得るものがあります。
チケット£5~40は安いですね。
イギリスでは幕間に飲食する割合が高い(ほぼ全員?)ので、我々にもすっかりその習慣がついてしまいました。
バーで隣に居合わせたイギリス人老カップル。
紳士の方はスニーカーにフリースのジャケットという軽装ながら、しっかり首には蝶ネクタイ。
イギリスにはやはり腐ってもなんとやらで、こういう伝統を守る人々が多いのは確かです。
老人に古き良きイギリスを見るおもしろい例として。
以前妻がカフェNeroのソファでコーヒーを飲みながら一人読書をしていると、向かいのソファにやって来たのは老紳士。
小汚いカフェの地下で、ティーバッグの紅茶を場違いなほどお上品にお飲みになり、飲み終えるときちんと服を整えステッキを持ち、帽子を片手に、
「Young lady, good day」
本から目だけを上げた無作法な妻に、ていねいにお辞儀をして帰って行かれました。
そんなイギリスの伝統とチャーミングな継承者たちに敬意を表して、我々もコンサートにはほんの少し小奇麗ないでたちで行くのでした。
14.Nov.2006
イリュージョン アート
イリュージョン アート
別段目新しいことではありませんが、おもしろいものをいくつか。
ひとつめ。
ジュリアン・ビーヴァーは、ロンドンをはじめ、世界各地の路上に3Dアートを創作しているイギリス人アーティストです。

しかるべき位置からのみ立体的な絵が見えるしくみです。
ふたつめ。
残像を利用したアート。
おおかた結果が想像できるものの、実際に見えてみると不思議でおもしろいです。
試してみて下さい。
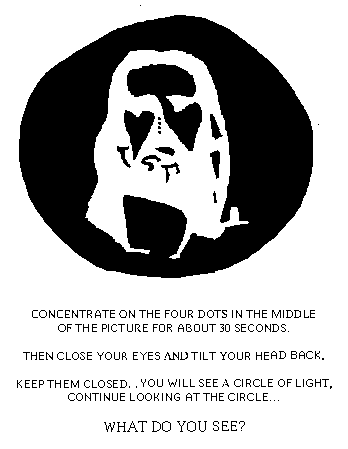
絵の中心の4点を30秒凝視します。
それから目閉じて(手で覆って完全に暗くするとよし)しばらく待ちます。
何かが見えて来ます。
みっつめ。
ペーパードラゴンというのがあります。
私も実際作ってみましたが、かわいいです。
こちらで動画が見れます。
ひとつめ。
ジュリアン・ビーヴァーは、ロンドンをはじめ、世界各地の路上に3Dアートを創作しているイギリス人アーティストです。
しかるべき位置からのみ立体的な絵が見えるしくみです。
ふたつめ。
残像を利用したアート。
おおかた結果が想像できるものの、実際に見えてみると不思議でおもしろいです。
試してみて下さい。
絵の中心の4点を30秒凝視します。
それから目閉じて(手で覆って完全に暗くするとよし)しばらく待ちます。
何かが見えて来ます。
みっつめ。
ペーパードラゴンというのがあります。
私も実際作ってみましたが、かわいいです。
こちらで動画が見れます。
London
カテゴリー
counter
ブログ内検索
愛読サイト&ブログ
FFFFOUND!
SHOWstudio
The Sartorialist
Style.com
松岡正剛「千夜千冊」
Jessica's classic music blog
lepli
classicFM
SHOWstudio
The Sartorialist
Style.com
松岡正剛「千夜千冊」
Jessica's classic music blog
lepli
classicFM
友人サイト&ブログ
LOHAS x MUSIC remiko's diary
ナニワのお琴弾き!片岡リサ
This is England
ミヤザキングダム
あなたの声に心は開く
I'm a dancer not one's perfect
ロンドン・アート・いろんな話
Kenta Kura Official Blog
Hani Sagiv
セレプな人々、セレプな日々
St.Barths PILATES IN LONDON
ERINEMと呼ばれて早3年
Moldavia
Yukibee in a tree
Kaori Kubo
Ine Tomokazu
Kana's Cafe☆New York
カレンダー
| 03 | 2025/04 | 05 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |